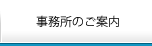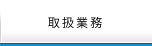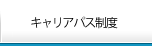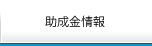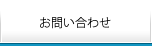Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】働き方改革~労働力人口と生産年齢人口

国連の資料によると、世界の生産年齢人口は2020年時点で50億8000万人。新興国を中心とする人口増で、50年には61億3000万人と20%増える見通しだそうだ。生産年齢人口とは、生産活動を中心となって支える人口のことで、15~64歳の人口のことだ。
日本の生産年齢人口は、戦後増加を続け、1995年にピークの8726万人に到達したが、それ以降は減少を続け、2015年には7728万人となっている。将来推計人口の出生中位推計の結果によると日本の生産年齢人口は、2029年に7000万人、2040年に6000万人、2056年に5000万人を下回り、2065年には4529万人となると予測されている。
一方、総務省が毎年発表している2017年労働力調査によると、2017年の労働力人口は6720万人となっている。このうち、6530万人は就業者で前年から65万人増加しており、完全失業者は190万人で前年から18万人減少している。労働力人口は2012年の6280万人から5年連続で増加しており、2007年から2017年までの10年間で2017年はもっとも労働力人口が高い年になっている。また、労働力人口における高齢者の割合が上昇し続けていることは特筆すべきである。
労働力人口と生産年齢人口との違いは何だろうか。労働力人口が満15歳以上で労働する意思と能力を持った人の数を指すのに対して、生産年齢人口とは15歳以上65歳未満の人口のことを指す。基本的には生産年齢人口の中に労働力人口が内包されるが、微妙に異なる。たとえば、生産年齢人口には含まれていても、労働する意思や能力の無い人は労働力人口に含まれない。一方65歳以上で働いている人は生産年齢人口には含まれないが労働力人口には含まれる。
今のところ、生産年齢人口は減少していても、労働力人口は増加しているが、女性や高齢者の労働力参加率の向上もいずれ頭打ちになり、長期的には少子高齢化によって生産年齢人口は大幅に減少するはずなので、労働力人口も大幅に減少すると考えられる。
ではその対策はどうすれば良いのか。まずは、高齢者のさらなる雇用の拡大であり、定年年齢の引き上げや、定年という概念を取りやめること。次に女性が働きやすい制度を拡充すること、子育てしながら働きたい女性が働きやすい雇用環境の整備すること。そして、非正規社員を正規雇用や格差是正すること、こうした身分制度を取りやめることではないだろうか。
【コラム】働き方改革〜同一労働同一賃金

2020年4月からは大企業を対象に、同一労働同一賃金のルールが適用される。働き方改革関連法として新しいルールがはじまっているなか、更に多様な働き方に対応すべき、社内制度の見直しなどの対応が迫られることになる。
施行されるのは、パートタイム・有期雇用労働法と改正労働者派遣法の同一労働同一賃金関係二法であるが、企業に正社員と非正規社員の不合理な待遇の格差を設けることを禁じるものである。業務内容や責任、配置や変更の範囲などに差がなければ、原則として賃金や手当、教育訓練などの待遇も同じ水準にすることが求められる。差がある場合は、社員の求めに応じて理由を説明する義務も生じることになる。
要するに身分の差を明確にせよとのことだろうか。日本の人事制度には、身分制度があり、その処遇や賃金が異なる。この身分制度を明確に定義し、その違いをはっきりさせるということを企業に義務付けるということなのだろうか。身分の違いが明確に理由づけることができると、処遇や賃金は異なっても良いということになる。
正社員、有期雇用労働者、パートそれぞれの役割などを就業規則で定義し、手当の目的や賃金の違いを整理しておくことが必要となる。とりあえずの対応は、これで済むのだろうが、根本的な働き方改革になるのだろうか。この身分制度がある限り、働き方の改革にはならないのではないだろうか。
定年制度や雇用によらない働き方、女性の働き方等の問題点や課題に、こうした身分制度を明確にする制度改革は、はたして労働生産性の向上に役立つのだろうか。この身分制度は、「時間」を基準にした労働の価値判断と通じる気がしてならない。時間基準の価値判断は、生産性の向上には程遠いと言われている。なぜ「知」や「能力」を労働の価値判断となる同一労働同一賃金にならないのだろうか。
【コラム】働き方改革〜「時間」や「年齢」による労働の価値

「知」が価値を持つ今は、年齢や肉体の衰えとは関係なく優れたアイデアを出す人が果実を得ると言われている。フランス革命と産業革命の時代を起源として、「時間」を企業にささげる働き方が雇用だった。それが脈々と受け継がれ現在に至っている。時間に比例して生産高や賃金が決まったもの作り時代の名残りが、弊害といわれ始めている。
若さや肉体に価値を置き、「時間」が雇用の基準としながら高齢化時代を迎え、定年という制度で次々と「引退」する世代を年金で支え続けることは難しくなっている。明らかに困難になってきているのに、いまだ主流の定年制を堅持し続けている。更に継続雇用という訳のわからない制度でごまかしを続けている。
年齢に関わらない能力による働き方と定年制は相反する。定年とは、肉体の衰えにより「時間」雇用の価値が下がるため雇用を終了するということなのだろう。継続雇用とは、「時間」雇用の単価を下げて契約をし直して再雇用するというシステムなのだ。年齢を基準に労働の価値判断していることによる弊害制度だ。
「時間」を基準に労働の価値を決めるのも時代錯誤だ。米国では組織に属さないフリーランスが2027年にも就労者の過半を占めるという予測もあるらしい。ただ自由な働き方を喜んでばかりもいられない。デジタル時代はスキルの陳腐化が格段に速まり、労働者の生活の安定性が揺らいでいく。「時間」も「年齢」も労働の価値判断にならないとしたら、どういう基準にカジを取るべきなのか。
技術が誕生するたびに一部の労働者は職を奪われたが、それを上回る需要が雇用を生んだ。時間や肉体ではなく知で勝負する時代には、働き手の「賞味期限」は延びるが、スキルは陳腐化し価値は下がる。「知」や「能力」を労働の価値判断とすべきなのか。そのスキルをどのようにして判断していくのか。その模索を急がなければならない。
【コラム】働き方改革〜2020年の働き方改革

経団連の中西宏明会長は日本経済新聞などとの年頭のインタビューで、「新卒一括採用、終身雇用、年功序列型賃金が特徴の日本型雇用は効果を発揮した時期もあったが、矛盾も抱え始めた。今のままでは日本の経済や社会システムがうまく回転しない。雇用制度全般の見直しを含めた取り組みが重要だ」また、「賃上げの勢いを保つことは大前提だ。ただ製品やサービスの付加価値向上に必要なスキルや意欲のある人が活躍できる環境づくりも大事だ。そのためには賃金体系や人事制度についてもしっかり対応すべきだ」等と述べた。
新卒一括採用、終身雇用、年功序列型賃金は、矛盾も抱え始め、うまく回転していないということだ。転職市場が発達せず、中途採用で優秀な人材を採用できず、雇用のミスマッチが起きモチベーションが下がった社員の解雇もできなく、社員の高年齢化による人件費の高騰になるからやめていこうということだろうか。
それでは、2020年の働き方のシステムは、どのように変革していけばいいのだろうか。中途採用や自由に転職できるようにし、あるいは成果の上がらない者は、簡単に解雇ができるようにして、成果を上げた者には手厚い賃金体系にしていけば、日本の生産性は上るのだろうか。手取り賃金は上がるのだろうか。そうは簡単にいかない気がする。
あくまで働く人それぞれの業務をいかに変えていくのかという意識が重要で、一人一人が自分の働き方を把握して、具体的に改善していくこと。スキルを磨き、自分のキャリアをどうしていくのかを明確にしながら働いていくこと。そして企業はそうした環境を整え、多様な働き方を受け入れ、その成果を還元していくシステムに変えていくことが必要だ。新年を迎えて具体的にどのような方策があるのかを考えていきたい。
【コラム】働き方改革〜残業代の還元

大企業の残業時間の上限が規制されるなか、減った残業代の分を社員に還元していない企業が2019年4~6月で5割に上ることが日本経済新聞の調査で分かった。多くの企業で残業を減らしながら生産性を高め、それに寄与した社員に報いるという循環に至っていない現実があるようだ。
残業時間を減らしながら社員に還元したと回答した企業の業績をみると、大半の企業で前年同期比で純利益が増えた。還元策を実施しながら業績を上げる好循環につなげている企業は一部にはある。基本給への上乗せ、各種手当の支給、賞与、自己啓発支援制度の拡充等で還元したり、還元していない企業の中では、生産性の向上を賃上げ交渉などの材料にする「間接的な還元」で実施する企業もあるようだ。
働き方改革は、何のためにやらなければならないのか。労働生産性が先進7カ国中最下位で50年も続いている。時間あたりでみた日本人の賃金が過去二十一年間で8%強減り、先進国中で唯一マイナスとなっている。我が国の国内総生産の相対的低下が続いているため、賃金低迷の状況が消費をさらに冷え込ませる悪循環を招いている。こうした状況を打破するためではなかったのだろうか。
働き方改革は、誰のためのものなのだろう。ただ単に残業時間を減らすのでは、生産性は向上しないし、事業を縮小しているようなものだ。事業を縮小しようとしている企業が、5割もあるということなのか、生産性を向上させ、減った残業代を社員に還元しない企業が5割もあるということなのか。
いずれにしても、これはある意味罪ではないか。何のための働き改革なのか。今一度問い直してみたい。社員が効率的に働いて残業を減らしたのであれば、生産性が向上した分を還元することが内需の好循環を回すカギとなる。それが企業の収益の向上につながるのではないだろうか。
【コラム】働き方改革〜150万円の壁

総務省の労働力調査によると、夫の年収が300万円以上の場合、年収が高くなるほど妻の労働力率(労働力人口の比率)は低下するそうだ。日経新聞によると、共働き世帯の妻の過半数が、配偶者特別控除で減額の基準となる年収150万円未満のパートタイムの働き方を選んでいる。一方で、夫の年収が高いほど「150万円の壁」を超えて働く妻の年収も高くなっていることが、ニッセイ基礎研究所の調査でわかった。としている。
夫婦ともに少しでも収入があれば、政府統計では「共働き世帯」として集計される。共働き世帯の妻は35~54歳が約6割を占める。また、共働き世帯の約7割に子がいる。妻の労働時間はパートタイム(週当たり35時間未満)が54.5%を占め、パートタイムで働く妻は育児中の年代や高齢期、子のいる世帯で多いという。年収を見ると、「150万円の壁」を越えずに配偶者控除を意識して働く妻が51.5%であり、「壁」を越えて働く妻では、年収300万円未満と年収300~700万円未満がそれぞれ2割、年収700万円以上が3%弱である。年収700万円以上の妻は、約6割が夫も年収700万円以上である。
これは、夫の経済力が高いと、夫の扶養の範囲内で働く妻が増えるように思われているなか、高年収の妻も増えているということだ。1人目の子で出産後に退職せずに就業継続する妻が多いことや、出産後の妻の就業率は上昇傾向にある影響などが考えられる。あるいは、労働時間が短くとも、例えば短時間勤務の正規雇用者等の比較的年収の高い妻が増えているのかもしれない。
女性の働き方は、子の有無や同居の家族構成の違いなどを考えると、その実態はあまりにも多様であることがわかる。人手不足の中で政府は女性の労働力に期待を寄せている。配偶者特別控除が減額され始める上限額が引き上げられ、「壁」の範囲が広がっているものの、「壁」を遥かに越えて働きたい女性の意識があることも見逃すことはできない。そのためには、職場の制度環境の整備に加えて、家庭環境の整備、特に男性の意識の変革も必要ではないだろうか。
【コラム】働き方改革〜職務分析

安倍総理大臣は、IMFの専務理事との会談で、日本経済を中長期的に成長させるためには、働き方改革など少子高齢化の進展に合わせた構造改革が必要だという認識で一致した。また、経団連の中西会長は、2020年の春闘について「生産性を上げるような働き方改革について議論したい」と述べ、賃上げに加え、生産性向上につながる働き方についても労使間で議論すべきだという考えを提示した。政府、企業ともに、生産性向上に向けた働き方改革の必要性を認識している点で一致している。
生産性を上げる働き方とは、労働時間をいかに少なくし、付加価値をいかにして多く勝ち取る働き方をするという事なのだろう。現在のやり方は、生産性が低いものだとの前提で考えなくてはならない。そのために、どのような方法で働き方を変えて行けばいいのか。
残業を抑制するために、強制的にパソコンをシャットダウンしたり、照明を切ったりすることでは、解決にならない。あくまで働く人それぞれの業務をいかに変えていくのかという意識が重要になる。一人一人が自分の働き方を把握して、改善していき、PDCAサイクルをまわしていくことが重要で、「有効に時間を活用して、浮いた時間で家族と過ごす時間を増やしたり、自分の能力を高めるための時間をつくったりすることができる」と個人が気づくことが原点となる。
こうしたことは、個人で進めることは、なかなか難しく、ICTベンダーで見える化ツールを提供しており、Panasonicが「しごとコンパス」、NECが「働き方見える化サービス」、富士通エフサスが「TIME CREATOR」を提供している。これらは、業務内容の見える化、作業時間、勤務時間の見える化を行うツールで、パソコン上のファイルやアプリケーションの操作ログ情報を取得して、ファイルやアプリケーションの操作にどの程度時間をかけているのか、集計することのようだ。
こうしたやり方は、社労士として昔から行っている「職務分析」に当たるもので、「職務記述書」や「職務明細書」と言われるものの元になるものである。「職務基準」による「職務給」と言われるものだ。仕事基準の人事制度である。なぜ、この国は生産性が低いのか。それは、多くの企業はこうした職務分析を行わず、何をどこまでやるのか具体的に示さず、明確な目標とか期待される成果を明らかにしていないためだ。
それを「今の労働者の働き方は、生産性が低い」と責任を押し付けていることは、ないのだろうか。企業自ら見える化ツールを利用して、職務分析を行い、やるべきことの基準と目標を明確にしていくことが重要ではないだろうか。
【コラム】働き方改革〜日本郵政グループの働き方

日本郵政の前社長は、西室泰三氏だ。あの株式会社東芝代表取締役社長であった方だ。ご存知の通り、2015年・2017年と、東芝に2度の不正会計問題を起こさせ、東芝を世界企業から倒産寸前の崩壊へと追い込んだ張本人と言っていい人物だ。しかし本人はこれらの責任を問われず、その後も東芝名誉顧問として東芝の経営に関与し続け、2013-2016年には、日本郵政社長の座にあり、豪州の物流会社トール・ホールディングスを6600億円で買収することを殆ど1人で決定したといわれるが、その結果日本郵政にも4000億円の巨額損失を与えた。
その後任の社長が、長門正貢氏だ。日本興業銀行に入行、2006年から富士重工業(現 : SUBARU)に移り、代表取締役副社長、2011年6月シティバンク銀行に移り、2012年1月同行取締役会長に就任している。こうした実績を評価され、2015年5月11日、ゆうちょ銀行社長に就任している。2016年4月1日付で、西室泰三日本郵政社長の病気による退任に伴い、日本郵政取締役兼代表執行役社長に就任した。
日本郵政グループは、調査によると、過去五年間で法令や社内規定に違反する疑いのある契約数は一万二千件を超えており、かんぽをめぐっては保険料二重払いや無保険状態の契約などが次々に発覚。今回の調査では、商品の虚偽説明など法令違反の疑いが濃い悪質な事例もあったとのことだ。不正の温床になったのは職員に対する過剰なノルマだ。
日本郵政のホームページのトップメッセージに次のように述べられている。
「…社員に対しては、給与水準と報酬水準をしっかりとしていくほかに、企業として、ダイバーシティ、介護、育児の課題を考えなければなりません。また、女性登用のみならずLGBTの差別や偏見に気を配らなければなりません。そうなると、クオリティー・オブ・ワーキングライフが必要なわけです。社員が幸福に出社してくれるような環境を整えたいですね。「チームJP」として、みんなで頑張ろうということです。これから来る新入社員に、あの会社に絶対入りたいと言われるような企業になることが目標です。」
なんとも悲しいメッセージを残しての辞任である。日本を代表する企業経営者の考えに、何か根本的に歪んだものがあるのではないか。こんなことでは、いつまでたっても働き方改革は進まない。
【コラム】働き方改革~官僚の働き方

衆院規則では、「議事中は参考のためにするものを除いては新聞紙及び書籍等を閲読してはならない」(第215条)とある。PCやタブレット端末、スマホについては明文化された規則はないものの、本会議場については215条を根拠に「持ち込みをご遠慮願っている」という。委員会室では、審議の参考に資する場合で、委員長の許可を受ければPCやタブレット端末を利用できる。参院は95年10月の議運の申し合わせで、本会議場、委員会室問わず、携帯電話の持ち込みを禁止している。PCやタブレット端末についても同様の運用とのことだ。
日経新聞によると、「霞が関の非常識 月100時間残業…」として、官僚の働き方を報じている。国会の会期中、役所の担当分野・法案について与野党の議員から審議での質問を聞きだし、閣僚らの答弁案をつくる。議員の質問通告は委員会を開く日の2日前の昼までが原則だが、大半は守られず、修正を重ねた大量の答弁案を印刷し、ホチキスでとじて、国会に自転車で届ける。審議の前はこの作業が延々と深夜まで続く。残業時間が月に100時間を超える職員は珍しくない。
こうした残業を余儀なくされている原因の一つが、このタブレット端末禁止ルールだ。「タブレットを使えば自宅で答弁の文言を修正し、内部で共有できる。完成版をすぐに届けられ、深夜の待機をなくせる」とのことだ。こんな古めかしいルールがまかり通っているとは、なんとも驚きだが、逆に国会らしいルールだ。
安倍内閣は、「働き方改革」と声高に叫んでいるが、足元の霞が関の状況はまったく改善されていない。霞が関はその「働き方改革」の旗振り役でもあるはずなのにである。人材という行政資源の浪費は日本の活力をそぎ職員の判断力や創造性の低下、人材の流出が続いているのではないか。学校法人「森友学園」への国有地売却をめぐる財務省の決裁文書改竄や、文科省を揺るがした加計疑惑、そして今回の桜を見る会のシュレッダー事件等、官僚の不祥事が続いている理由は、こうした安倍内閣の姿勢にあるのではないだろうか。
【コラム】働き方改革~男性の育児休暇

国家公務員の男性に育児休暇・休業の取得を促すため、政府が検討している新たな取り組みがわかった。子供が生まれた男性職員の上司に育休取得に責任を持たせる。1カ月以上の取得を推奨し、職員の意向に基づいた取得計画を作成する。実効性を高めるため管理職の取り組みは上司の人事評価に反映する。
三菱UFJ銀行では、10営業日の短期の育児休業と、通常の有給休暇などを合わせて約1カ月の長期育休を男性行員に促す。部下が育休を取れているかどうかを上司の人事評価の対象とし、制度利用を促す。また、積水ハウスは18年9月から男性社員に1カ月以上の育休取得を義務付けた。日本生命保険は13年から6年連続で男性社員の「育休取得率100%」を達成している。
厚労省雇用均等基本調査(平成27年)によると、男性の育休取得日数は「5日未満」が56.9%と突出し、次いで「5日~1カ月未満」は26.2%で、「1カ月以上」は16.7%だという。平成30年時点での男性の育休取得率は6.16%にとどまっているようだ。ノルウエーでは、2012年以降には男女ともに90%を超えており、スウェーデンも男女とも80%前後までになっている。ドイツの場合、2016年には男性が、34.2%まで伸びた。「両親手当」により、育児休暇中でも給料の67%の給付金を受け取ることができるようになったと聞く。
日本でもよく知られていないが、「パパ・ママ育休プラス」という制度があり、条件を満たした場合、育休期間を最大2ヶ月引き延ばすことができ、パパも給付を受けることができる。ただ、利用者の割合は低く、女性の復職者のうち、パパ・ママ育休プラスの利用者割合は 1.9%、男性は 3.0%であった。
昨日のコラムで書いた日本の出生数は、統計開始以来の最低数となった。男性の育休取得は、国の運命をも決める少子化問題の解決策の大きな一つになり得るのではないだろうか。多くの企業で、こうした先進的な取り組みを進めていくことが、女性が活躍できる職場環境の整備と働き方改革につながることになるのではないか。
« Older Entries